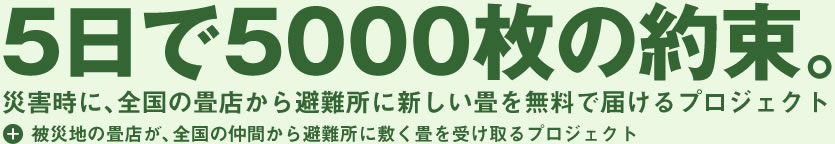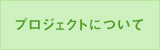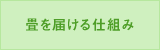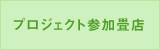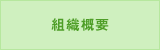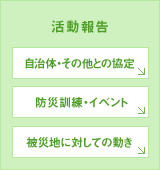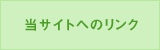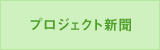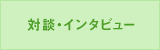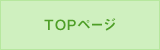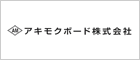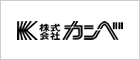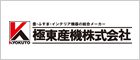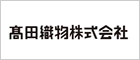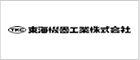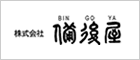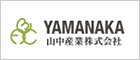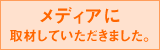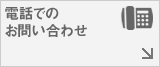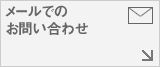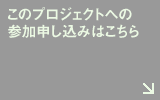004・須磨の漁師さん

▲左から当プロジェクト事務局長・前田、奥谷知生氏、幸内 政年氏、若林良氏
自分たちで海を守ると日ごろから積極的に活動される漁師さんたち。兵庫県神戸市にある須磨海岸で海の家を営みながら様々なイベントを主催している幸内氏をはじめ、漁師の奥谷氏、すまうら水産の若林氏に参加いただき、当プロジェクト事務局長・前田が活動への想いを伺いました。
《 話し手 》
 |
 |
 |
||
| 海の家・カッパ天国代表 幸内 政年氏 |
漁師 奥谷 知生氏 |
すまうら水産 若林 良氏 |
【 生業そのものが地元を守る。】
「これは僕たちの責任なんだけど、いろんなことを伝えていかないと地元は盛り上がらないし、町がひとつになることもない。」(幸内氏)
前田:船長(奥谷さん)のFacebookの投稿、いつもきれいな海の写真がいっぱい。
奥谷:海行って遊んでるやろ!ってよく言われる。(笑) 仕事のことより、須磨の海をもっと知ってほしいと思ってね。毎日海の顔が変わるから。昨夜の海なんてベタナギで最高やったよ。海抜ゼロから見る景色、みんなに見てほしいわ。
前田:でも夜中にひとりで海に出るって怖いでしょ。
奥谷:これが仕事だし。もちろん、急に景色が変わることもあるし、死にかけたこともある。一瞬で霧に囲まれて周りが見えなくなってることもあるし。
前田:須磨って、須磨海岸などの賑やかなイメージが先立ちます。地元の人にとって須磨ってどんなところなんでしょう。
幸内:地元の人ほど、須磨について知らないことがいっぱいあるんじゃないかな。海苔工場見学ができることとか。地引網ができることもそう。 これは僕たちの責任なんだけど、いろんなことを伝えていかないと地元は盛り上がらないし、町がひとつになることもない。接点を作らないとなにも始まらない。
前田:だから次々と新しいイベントをされるんですね。
幸内:漁師のコミュニティって仲間同士でガチガチですから。阪神淡路大震災の時も、せっかく大阪の漁師さんが運んでくれた支援物資を、受け取る側で配り切れずに腐らせてしまったこともあるんですよ。あんなことはもうやりたくない。まずもって、この須磨に漁師がいることを知らない人がたくさんいますからね。
前田:そうですよね。私も皆さんにお会いするまでは須磨の漁業って知らなかった。イベントに参加させてもらって、初めて知った感じです。
幸内:でも漁師って怖いイメージあるでしょ?
前田:はい、確かに怖い…。船長(奥谷さん)とか、初対面だと絶対に話しかけられない。
奥谷:みんな優しいんだけど、上手じゃないから。(苦笑)
前田:でも、みんな仲良しですよね。若林さんも積極的にいろいろと活動されているようですけど。
若林:須磨は新しいマンションがいっぱい建って、初めて須磨に住む人が増えたんですよね。
そういう新しく須磨に住まれる人達との距離を縮めたい。このあたりの海苔漁師も震災前よりだいぶ減って…そういう危機感があるからかな、みんなで地域と交わろうとしています。それに、お父さんが漁師だってこと、自分の子ども達にも胸を張って言ってもらいたいしね。
前田:なるほど。
「まずは自分たちでやるしかないと思ってる。 」(若林氏)
若林:最近は自治しているって意識もだいぶ強くなってきました。大切な場所として須磨の海を守っていこうっていう意識。イカツいプレジャーボートとかこの辺りにきたら、毅然と対応するしね。
前田:怖くないんですか?
若林:そりゃ怖いですよ。でも、ひとつ許すとあとに示しがつかない。
前田:男前!
若林:もちろん、そうやって他人に意見するわけだから自分たちも律しています。漁師の特権とかいってここでBBQとか、焚火なんかも一切やらないし。
前田:若林さんたちがそういう対応をしていること、行政の方は知ってるのかな。
若林:どうかな。でも、まずは自分たちでやるしかないと思ってる。
幸内:そうやね、行政に頼らなくってもできるようにならないとね。むしろ、こちらが行政に協力しないといけないんじゃないかと思う。
前田:行政に協力する?
幸内:そう。僕は地域の声を代弁したいと思ってる。僕たちはこんな未来を描いているんだっていうのを広く伝え続けたい。ゆっくりね。多くの人に体験漁業をしてもらって、また違う須磨を感じてもらったり。
前田:船長(奥谷さん)もどこに行っても顔を見ますね。防災イベントの時は、漁師のロープの縛り方を活かしたり。
奥谷:俺も須磨のこと、もっと知ってもらいたいしね。それに若い漁師たちともこれからのことを共有していきたい。これからのことっていうか、自分なりに感じている「危機感」みたいなこと。このまま自分達本位やったらアカンってとこ。みんなで共有しながら一緒に伝えていきたいねん。
捕ってきたばかりの魚とかプールに入れて、子どもたちに触れさせるでしょ。
そのあと俺が魚をシメルと、子どもたち泣くけど。でもすぐにめちゃくちゃ美味しそうに食べてる(笑)。そんなことでも子ども世代から少しずつ伝えていきたい。
「須磨の海の仲間としてその姿みたらなんとかサポートしたい。やってると、今まで会えなかった人にも会えるようになってきた。」(奥谷氏)
前田:幸内さんは海の家を営まれながら船長や若林さんと一緒にイベント活動をされています。地元の漁師さんたちと始めるのは大変だったのでは?
奥谷:最初はみんな抵抗あったよ。なんでそんなことせなあかんねん、とかもあった。
前田:でも今は幸内さんがされるイベントはみんなが一緒に汗かいてる。幸内さんに共感してます?
奥谷:そうやね。彼は準備から片付けまで一人でやって、しんどい思いばっかりしてるしね。須磨の海の仲間としてその姿みたらなんとかサポートしたいしな。
でもやってると、今まで会えなかった人にも会えるようになってきた。彼の言うとおりになってきたと思ってる。
若林:そうそう、今まで魚屋さんとしか繋がりなかったのに、幅が広がった。今は人との繋がりが財産やと思ってる。
前田:ガチガチが徐々にほぐれてきたのかな。
幸内:元々、ぼくも漁師だしね。漁師を辞める理由が、自分は漁師としては無理だけど、この須磨の漁師さん達を世の中ともっと近くすることが自分の使命だと思ったから。単純にその想い(使命)のまま進むことができています。漁師仲間って、めちゃくちゃ優しいし、助け合いの精神が根っこにあってね。
前田:そうですね。
幸内:とにかく新しい接点を作ること。それが自然にほぐれながら進むといいなと思っています。
仲良くすれば何でもうまくいくから。地元が仲良いとまわりの人から、いい地域だねって言われるんですよ。そしたら地元の人も嬉しいって言ってくれてるし。そういうことなんだなって思っています。
前田:みなさんの生業そのものが地元を守っているんですね。地元を守るって言葉、軽々に使えなくなりそうです。すべてではないですが、よくある“まちづくり”とは成り立ちや方法が違いますね。
幸内:須磨で生業を営んでいるからこそ、できること。全国の畳店さんの活動と同じだと思っていますよ。
前田:ありがとうございます。
(対談:2018年03月)
あとがき
『地元を守る』
たとえば「寄り添う」という言葉、悪い言葉ではないし、もちろん良いことなのですが、被災地で何度か耳にして、場合によっては逆によそよそしく軽く聞こえたり。漁師さん達の日常と取り組みをうかがいながら「地元を守る」という言葉も軽々に言えないなと思わされました。
賑やかな須磨に流されてしまいそうなところ、埋もれてしまいそうなところに危機感をもって、言い訳せず、誇りを持って、自律して、助け合って。
よく用いられる「まちづくり」とも成り立ちが違うような、シンプルで地元への感謝と愛着から成る姿勢と言葉に教わったように思います。
今までのつながり、これからの新しいつながり。そんな日常の積み重ねが災害に限らずいざというときの備えに成る。『地元を守る』とは、それぞれが役割を認識し、そこに根を張り、考え続け、行動を続け、なりわいを続けることなのかもしれません。
(事務局長・発起人 前田敏康)